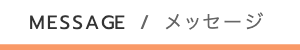「全ての有形は無形から象ずる」
当団体は社会的に行政が届きにくい案件の当事者からの声に、無償のサービスを提供したり、それぞれの地域社会の抱える問題を迅速に人が解決する活動をしております。
「仕事のための人生ではない。」
都市部は「仕事中心の生活スタイル」ローカルは「生活中心の仕事のスタイル」と考えています。
現在集った仲間は地域で自立し、支え合う事を理解し活動しています。
行政に不平不満を言う前に、まず地域の問題と捉え、地域の支え合いで解決をする方法を提案しています。
地域の自立には必要以上に補助金や助成金などに安易に頼らないことも大切なことと捉えています。
助成金や補助金投入で自立が阻害されている面を多く感じました。
助成金などセミナーと称し様々な提言などされてますが、どれも正しく地域を理解することもなく、即効力もなく効果が疑問視されています。
その補助金は地元に直接お金を落させないシステムであること。
お金が全てを解決するのではなく、多くは人で解決できることもたくさんあります。
私たちはその人材を作ることが一番の底力になると考えています。
好きな場所で生活をしたい、その発想が新しい事業を生み出し提供する側も受ける側も自治としてみんなが喜べると考えています。
私たちはその条件で自立していけるか、その可能性を確かめるため、2013年「高島LOVERS」という団体を立ち上げ活動をはじめました。
2017年法人化
2013年に離島ローカルライフ挑戦を始め、地域活動を行っていく中で、島民の皆様は温かく協力も頂き、私たちは過疎でも自立していける可能性を感じ、2017年10月に一般社団法人LOVE LOCAL JAPANを設立しました。
Local LiFEの原点

将来に向けて新しい土地の暮らしには、震災や避難生活などの経験を踏まえてスタートしました。
便利な都市部が果たして安全な街なのか?
便利なことは本当に人間の暮らしや心を豊かにしているのか?
今の時代を全てシンプルに考えて活動を始めました。
・なぜ島なのか?
2023年令和5年9月末
人口271人・193世帯
男性131人・女性140人
以前の都市部の便利な生活スタイルから、不便を伴う島暮らしが果たして可能なのか、当初は不安だらけでした。
2011年6月に九州入りし、佐賀県鳥栖市で2013年2月まで生活、それまで毎日のように帰還か、鳥栖へ留まるか、移住場所を新たに探すか?そればかり考えていました。
生活費もままならない状況が刻々と近づきつつあったことも早く決断しなければいけなかった。
東日本大震災・原発事故を経験した者として教訓にした人生でなければいけないと実感しました。
・子供優先の生活環境確保
・ 便利な都市生活は災害に弱い事実
・自治に甘える事なく自立し、地域が支え合う生活をする事
そして決断は、少子高齢、人口減少の過疎の離島生活を選択。
それはシンプルに人口が少ない方が支え合うことを実感できる、都市部から隔離された島が最適な条件だったからです。
・移住から5年(2018年所感)
当初移住し苦しかった時期が長かったですが、努力し島の環境を学び、知恵や経験を生かして乗り越えていくしかないと腹を決めました。
子供の笑顔のためにも家族のためにも、苦しいことに向かって進まなければならなかった。
悩んだりしている余裕もありませんでした。
「困難は自分で考え乗り越えるしかない」と、ローカルライフで学びました。
生活していく中で地域の優しさに触れ子供を大切にしてくれた島民の皆様の気持ちに感謝し、地域の活動していこうという思いになりました。
誰も経験していない新しい時代を生き抜く方法を、この島で学び実践し結果も出せるようになりました。
現在の生活環境から抜け出したい人のために、自分らしい人生を生きたい人のために、微力ながら僕らの経験が活かせるように共有したいと思っています。
・移住から10年(2023年)
2019年年末辺りから始まったコロナ禍の3年で生活環境も事業も大きなダメージを受け、この島だけではなく日本全国、生活スタイルを根本から考え直すきっかけになりました。
事業の見直しなど1年ごとに試行錯誤を繰り返しながら現在も島で学んだことを基本に再構築をしています。
これからのローカル
長崎市高島という産業衰退から人口減少・施設の老朽化・少子高齢化など経過時間から多くのことを学びました。
現在日本は人口減少・少子高齢化・ハコ物の老朽化の3点は逃れられない時代に入っていることも同時に起きていました。
補助金助成金で運営されている島のお金の使い方、昭和時代への逆行した発想では解決できないことも明白な事実です。
当団体所在地の長崎市は、もともと税収基盤が脆弱で20年以上長引く景気低迷の影響もあり、市の税収入は減少傾向にあり、今後は人口減少や地価の下落などにより、市の税減収が平成29年度予算などにも現れています。
また今後全国的にも拍車がかかる、昭和の時代の箱物と言われる行政管理の建物の老朽化による保守、解体、メンテナンスなど増大する費用負担は免れられない状況にあります。
扶助費は高い水準で推移するものとして、合併により配布されていた合併歳も平成32年(2020年)で打ち切られ、合併により増額されていた地方交付税が段階的に縮減されることから、行財政改革による人員削減や積極的な事業の見直し等の改革を進めていかなければ、厳しい財政状況となることが確実視されています。
助成金事業や委託事業など税金負担の事業などは収縮し、地方の行政サービスも大幅に縮小されていくことでしょう。
減収してく財政は今後、そこに住む住民が個人負担していかなければいけない状況はすでに出始めています。
国の政策も地方へ負担が多くなっており、ローカルは自立の道を早めなければいけないと感じます。
日本は成熟しゼロ成長を目指すのではと思っておりましたが、相変わらず大量生産大量消費のままで、もはや資本主義が時代の格差を生み出し、この国の経済はいつか浮上するという甘い考えは誰の目にも明らかな様に下降線の一途を辿っています。
今後困窮する日本各地のローカルで起こり得ていることを誰よりも早く察知し、今からその対策に備えていくことが必要だと考えています。
ローカルはそこに住む人々で支え合いながら、必要以上のものは求めず、足りないところへ回すなど、その地域で循環できる経済を目指したい。
今までの様な都市部に依存する生活スタイルを改め、ローカルの場で出来ることを積極的に行いたいと思っています。
ローカルだからこそ自立できる。
「足るを知る」ことを知る、これに尽きるのだと感じます。